定款および関連規則
当協会へのご質問やご意見がございましたら、お問い合わせください。
第1章一般規則
第1条 (名称)
この法人は「東洋書道協会」(以下「協会」といいます)と呼ばれています。
第2条 (場所)
① 本会議の本部はソウルにあります。
② 本会議の支部(支部)は 1.光州支部 2.清州支店 3.忠州支店は、その他の必要な場所(各市と省)に支店と支店を置いて設立されました。
第3条 (目的)
韓西グループの創造的自立を確立するために、この会議の目的は、東洋文字芸術の基礎である漢字文化諸国 (韓国、中国、日本) との友好を促進し、ハングルなどの書体の開発を通じて世界中の芸術に昇華させ、21世紀の新しい書家を開拓することで芸術教育と書道の育成に貢献することです。
第4条 (事業)
上記の目的を達成するために、以下のプロジェクトが実施されています。
- 韓国、中国、日本の合同展や全国コンテストの開催による新進アーティストの発掘
- 書道文化を紹介する国内外の交流展や学術発表会
- 韓国語書体開発の促進
- 書道に関する外国文献の調査と出版
- 本会議の目的を達成するために必要なその他のプロジェクト
第2章メンバーシップ
第5条 (会員の資格)
本会議の委員は、本会議設立の目的を承認し、所定の入会申込書を提出して理事会の承認を得た者とする。
第6条 (会員の権利))
会員は、総会を通じて本会議の運営に参加する権利を有する。ただし、準会員、特別会員、名誉会員は総会に出席して発言することはできますが、議決権はありません。
第7条 (会員の義務)
会員には以下の義務があります。
- 定款および本会議規則の遵守
- 総会および取締役会の決議の実施
- 会費と控除額の支払い
第8条 (会員退会)
会員は、委員長に退会書を提出することで自由に退会することができます。
第9条 (会員特典)
① 本会議のメンバーとして、本会議の発展に貢献した者には、理事会の決定により報奨を与えることができる。
② 理事会議長は、総会の構成員として、理事会または総会の決定により、本会議の趣旨に反する行為をした者または第7条の職務を履行しない者を解任または叱責することができます。
第3章役員
第10条 (役員の種類と人数)
総会は以下の役員を任命する。
- 代表取締役 1 人
- 会社のメンバー15名(会長を含む)
- 2 件の監査
※ 取締役の人数は5名以上とする。
第11条 (役員の選任)
① 役員は総会で選任され、その就任を遅滞なく所管官庁に報告しなければならない。
② 役員は、欠員が発生した日から2か月以内に選出されなければなりません。
③ 新役員は、任期満了の2か月前までに選出されなければなりません。
第12条 (役員の解任)
役員が、次の各号のいずれかに該当する行為を行った場合、総会の議決を経て解任されることがあります。
- 本会議の趣旨に反する行為
- 役員間の紛争、会計詐欺、または重大な違法行為
- 本会議の業務を妨害する行為
第13条 (役員の選任の制限)
① 役員の選任にあたっては、民法第777条に規定する互いに関係のある役員の数の5分の1を超えてはならない。
② 監査人は、民法第777条に規定されているように、監査人または理事との間に親族関係があってはなりません。
第14条 (専務理事)
① 本会議の目的に焦点を当てるため、常任理事を任命することができる。
② 事務局長は、理事会の議決を経て、理事の中から選任される。
第15条 (役員の任期)
① 役員の任期は4年とする。
② 選挙により選任された役員の任期は、前任者の残任期間とする。
第16条 (役員の義務)
① 議長は総会を代表し、総会の業務を監督し、総会および理事会の議長になります。
② 取締役は、取締役会に出席して総会の業務に関する事項を議決し、取締役会または会長から委任された事項を処理します。
③ 監査人は以下の職務を行います。
- 本会議の財政状況の監査
- 総会および理事会の運営および業務に関する監査事項
- 第1号および第2号の監査結果に誤りまたは不正があることが判明した場合は、取締役会または総会に訂正を求め、国家行政に報告する必要があります。
- (3) の訂正および報告を求める必要がある場合、総会または取締役会の招集を要請すること
- 本会議の財政状況と業務について、総会、取締役会、または取締役会会長に意見を述べる
第17条 (委員長の代理)
① 委員長が事故に遭ったときは、委員長が任命した理事が委員長に代わって行動しなければならない。
② 委員長が解任された場合、委員長の職務は長老の順に理事に代わって行われる。
③ 第2項の規定により、会長に代わって行動する取締役は、遅滞なく議長の選任手続きを行わなければなりません。
第4章総会
第18条 (総会の構成)
総会は本会議の最高議決機関であり、メンバーで構成されています。
第19条 (分類及び招集)
① 総会は、定例総会と臨時総会に分かれており、理事長が招集します。
② 定例総会は各事業年度の開始1ヶ月前までに招集し、臨時総会は会長が必要と認めたときに招集する。
③ 総会を招集する場合、議長は会議の議題、日付、場所を指定し、会議開始の少なくとも7日前までに各メンバーに書面で通知しなければなりません。
第20条 (総会の招集に関する特例)
① 次の各号のいずれかに該当する招集請求があった場合、議長は招集請求の日から14日以内に総会を招集しなければならない。
- 職員の過半数が会議の目的を提案し、招集を要請したとき
- 第16条 (3) (4) の規定により監査の招集を求められた場合
- 現会員の5分の1以上が会議の目的を提示し、招集を要請した場合
② 総会を招集した者の脱退により、7日以上にわたって総会を招集することが不可能な場合は、現会員の過半数または現会員の3分の1以上の承認を得て総会を招集することができる。
③ 第2項の規定による総会は、出席年数の長い理事会の委員長を選出する。
第21条 (決定定足数)
① 総会は、現職議員の過半数の出席をもって決定し、出席議員の過半数の承認を得て投票する。
② 会員の議決権は、総会に出席する他の会員に書面で委任することができます。この場合、総会の開始前に委任状を議長に提出しなければなりません。
第22条 (総会の機能)
総会は、次の事項について議決するものとする。
- 役員の選任及び解任に関する事項
- 役員の選任及び解任に関する事項
- 基本資産の処分及び取得並びに資金の借入に関する事項
- 予算と決済の承認
- ビジネスプランの承認
- その他の重要なポイント
第23条(総会の決定を却下する理由)
会員は、次の各号のいずれかに該当する場合、投票に参加しないものとする。
- 役員の選任及び解任における自己に関する事項の議決を行う場合
- 金銭若しくは財産の徴収又は訴訟に関する事項により、本会議と自己の利益が相反する場合
第5章理事会
第24条 (取締役会の構成)
取締役会は、会長と取締役で構成されています。
第25条 (分類及び招集)
① 取締役会は、通常の取締役会と臨時理事会に分かれており、会長が招集します。
② 定例取締役会は、各事業年度の開始前の1月までに開催し、会長が必要と判断した場合は暫定取締役会を開催する。
③ 取締役会の議長は、会議の議題、日付、場所を指定し、会議開始の少なくとも7日前までに各取締役および監査人に書面で通知しなければなりません。
第26条 (取締役会の招集に関する特例)
① 理事会長は、次の各号のいずれかに該当する招集請求があったときは、招集請求の日から20日以内に取締役会を招集しなければならない。
- 職員の過半数が会議の目的を提案し、招集を要請したとき
- 第16条 (3) (4) の規定により監事の招集を求められた場合
② 取締役会を招集した者が棄権または回避したために7日以上にわたって取締役会を招集することが不可能な場合は、取締役会のメンバーの過半数の承認を得て取締役会を招集することができます。
③ 理事会は、第2項の規定に従い、最年長の出席理事会の下で会長を選出する。
第27条 (書面による決議の禁止)
取締役会の決定は書面による決議に基づくことはできません。
第28条 (決定定足数)
① 理事会は、現在のメンバーの過半数の出席をもって決定し、出席している理事の過半数の承認を得て投票する。ただし、夫婦の場合は、議長が決定します。
② 取締役会の議決権を委任することはできません。
第29条 (理事会の決議)
理事会は、以下の事項について審議し、議決するものとする。
- 業務執行に関する事項
- 事業計画の運営に関する事項
- 予算及び財務諸表の作成に関する事項
- 定款の変更に関する事項
- 財産管理に関する事項
- 総会に提出する議題の準備
- 総会から委任された事項
- 定款の規定によりその権限に該当する事項
- その他議長が本会議の運営上重要と認めた事項
第6章財産と会計
第30条 (財産の分類)
本会議の財産は、以下のように基本財産と普通財産に分けられます。
- 基本財産とは、協会設立時に創設者が出頭した財産であり、理事会で基本財産として決定された財産であり、一覧は「別表1」のとおりです。
- 普通財産は基本財産以外の財産とする。
第31条 (基本財産等の処分)
本会議の基本財産の処分(売却、贈与、交換を含む)を希望する場合は、第40条の規定に従って定款変更許可の手続きを行う必要があります。
第32条 (収益)
本会議からの収益は、会員の会費およびその他の収入によって賄われるものとします。
第33条 (会計年度)
本会議の会計年度は、政府の会計年度に従います。
第34条 (予算編成)
本会議の歳入支出予算は、各事業年度の開始1か月前までに作成され、理事会の議決を経て総会の承認を得て決定されます。
第35条 (和解)
総会は、各事業年度終了後2か月以内に財務諸表を作成し、理事会の議決を経て総会の承認を得るものとする。
第36条 (監査)
監査は少なくとも年に2回実施する必要があります。
第37条 (役員の報酬)
報酬は、業務の運営に専任する執行取締役以外の役員には支払わないものとする。ただし、業務遂行に要した実費は支給できます。
第7章オフィス
第38条 (事務局)
① 議長の指示の下、本会議の事務を処理する事務局を設置する。
② 事務局には、理事1名と必要な職員を配置することができる。
③ 事務局長は、理事会の議決を経て会長が任命する。
④ 事務局の組織及び運営に関する事項は、理事会の決議の上、別に決定するものとする。
第8章救済策
第39条 (法人の解散)
① 総会が解散を希望する場合、総会は、現在の会員の少なくとも3分の2の賛成を得て解散の議決を行い、その解散を管轄官庁に報告しなければならない。
② 総会の解散時における残存資産は、国又は地方公共団体又はその他の非営利法人が総会と同様の目的をもって所有するものとする。
第40条 (定款の変更)
これらの定款を変更する場合、総会は現在のメンバーの少なくとも3分の2に賛成票を投じ、州政府から許可を得る必要があります。
第41条 (ルール制定)
本定款に定めるもののほか、本会議の運営に必要な事項は、理事会の議決を経て規則により決定するものとする。
補遺
第1条 (効力発生日)
これらの定款は、州政府の許可を得て裁判所に登録された日から有効になるものとします。
第2条 (経過措置)
本定款の実施に際し、主催者等が法人を設立するために行った行為は、本定款に従って行われたものとみなす。
第3条 (創設者の名前と印鑑)
本会を設立するために、本定款は創設者全員によって以下のように作成され、署名されています。
役員登録の変更
: 2016.11.4。定款変更許可 (委員長の任期から理事長の任期へ) 文化スポーツ観光省
: 2016. 11.24 登録 (最高裁判所)
제1조 (목적)
본 규정은 동양서예협회(이하 "협회"라 한다)의 회원 자격, 회비 체계 및 납부 절차 등을 명확히 규정하여 협회의 건전한 재정 운영과 회원 간 형평성을 확보하고, 동양 서예 문화의 발전에 기여함을 목적으로 한다.
제2조 (회원의 종류 및 정의)
① (회원의 구분) 협회의 회원은 납부 의무에 따라 다음과 같이 '일반회원'과 '평생회원'으로 구분한다.
가. 일반회원: 협회에 가입하여 본 규정 제3조에 명시된 연회비를 매년 납부하는 회원
나. 평생회원: 협회에 가입하여 본 규정 제3조 3항 또는 제4조에 명시된 평생회비를 일시(또는 분할) 납부하여 연회비 납부 의무를 영구히 면제받은 회원
② (회원의 등급) 제1항의 회원은 협회 활동 경력 및 성과에 따라 다음과 같은 등급을 부여받으며, 등급에 따른 권리와 의무는 이사회에서 별도로 정한다.
가. "청년작가": 40세 이하 작가로서 협회의 이념과 목적에 동의하는 자
나. "일반작가": 41세 이상 작가로서 협회의 이념과 목적에 동의하는 자
다. "추천작가": ⟪추천ㆍ초대작가 선임 규칙⟫에 의거 3년 이상 청년작가 혹은 일반작가 회원으로 활동하고 협회 수상작 기준 입상 점수 15점 이상을 취득한 자로서 이사회의 심의를 거친 자
라. "초대작가": 청년작가, 일반작가 혹은 추천작가로 3년 이상으로 활동하고 협회 수상작 기준 입상 점수 15점 이상을 취득한 이후 추가 2회 이상 출품하신 자 중 이사회의 최종 승인을 받은 자
마. "임원": 초대작가 중 임원으로서 요구되는 별도의 활동 기준(예: 지난 3년간 협회 주요 행사에 5회 이상 참여, 특정 위원회 활동 등)을 충족하고 이사회의 추천과 총회의 만장일치 승인을 거쳐 임명된 자
제3조 (회비 및 등록비 기준)
① 연회비

② 등록비 (가입 및 승급 심사 시)
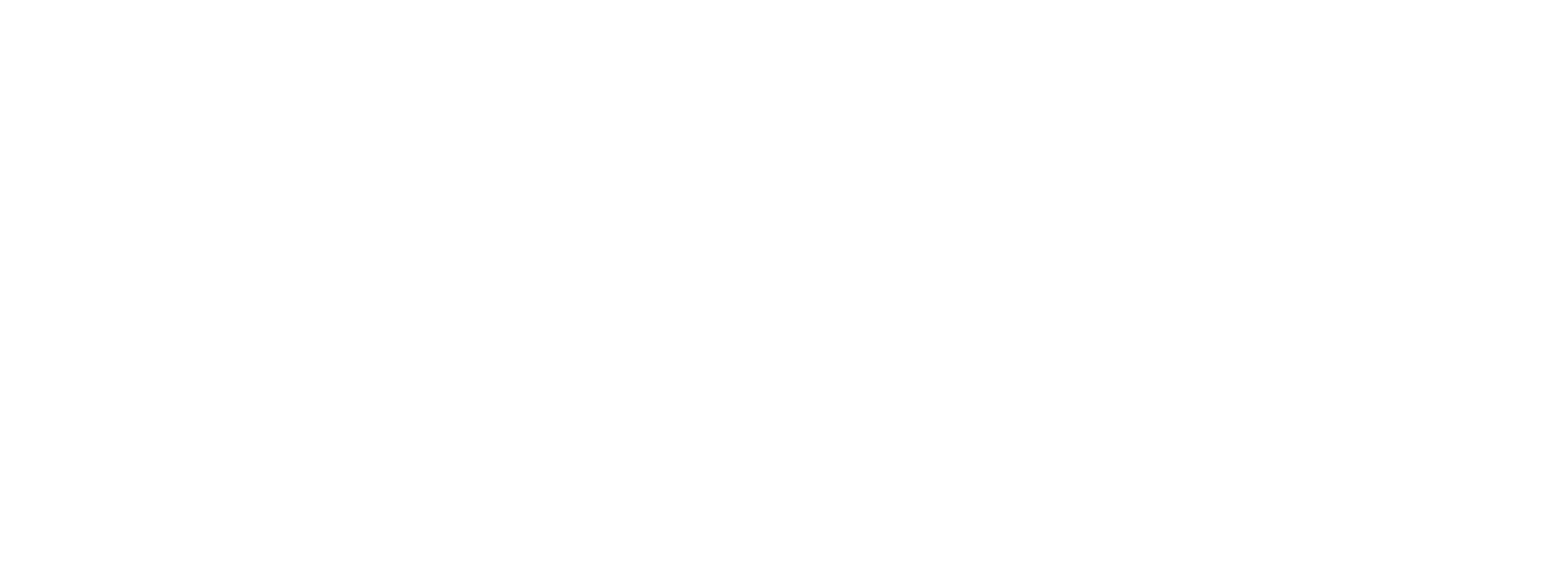
③ 평생회원
가. (자격) 본회의 정회원(초대작가)은 누구나 평생회비를 납부하고 평생회원 자격을 신청할 수 있다.
나. (회비) 평생회비는 연회비(제3조 제1항)의 10배에 해당하는 금액으로 책정한다.
다. (임원 특례) 제4조에 따라 발전기금 200만원을 납부한 임원은 본 조의 평생회비를 완납한 것으로 간주하여 자동으로 평생회원 자격을 부여한다.
라. (혜택 및 자격 유지) 평생회비를 완납한 회원은 납부 시점의 등급이나 향후 승급 여부와 관계없이 '평생회원' 자격을 영구히 유지하며, 이후 '연회비'(제3조 제1항) 납부 의무를 영구히 면제받는다.
마. (승급 시 의무) 단, ‘라’ 항의 연회비 면제 혜택과 별개로, 평생회원이 상위 자격으로 승급할 경우 '승급 등록비'(제3조 제2항)는 본 규정에 따라 별도로 납부하여야 한다.
제4조 (임원 발전기금 및 혜택)
① 임원으로 취임하는 정회원(추천작가 및 초대작가)은 협회 발전을 위해 발전기금 2백만원을 납부하여야 한다.
② 발전기금은 최대 20개월까지 CMS를 통해 분할 납부가 가능하다.
③ 제1항에 따라 발전기금 2백만원을 완납한 정회원은 '평생회원' 자격을 자동으로 취득하며, 이후 연회비 납부 의무를 영구히 면제받는다.
④ 제3조 3항에 따라 이미 평생회원 자격을 취득한 회원이 임원으로 위촉될 경우, 제1항의 발전기금 2백만원에서 기(旣)납부한 평생회비를 공제한 차액을 납부하여야 한다.
제5조 (회비 납부 기간 및 자격 관리)
① 연회비는 매년 1월 31일까지 납부함을 원칙으로 한다.
② 연회비 미납에 따른 조치
가. 1차 미납 (당해 연도 연회비 미납 시): 미납 사실 통보 후, 회원 활동에 필요한 권한(예:
웹페이지 접속, 특정 행사 참여 등)이 제한됩니다.
나. 2차 미납 (연속 2년 미납 시): 회원 자격이 정지되며, 모든 회원 혜택 및 권한이 중단됩니다.
다. 3차 미납 (연속 3년 미납 시): 회원 자격이 상실(제명)됩니다.
③ 미납 연회비 완납 후 기존 자격 복원 가능.
④ 특별한 사유 시 이사회 승인으로 납부 유예 또는 분할 납부 가능.
제6조 (출품비 규정)
.png)
제7조 (개인전 출품비 규정)
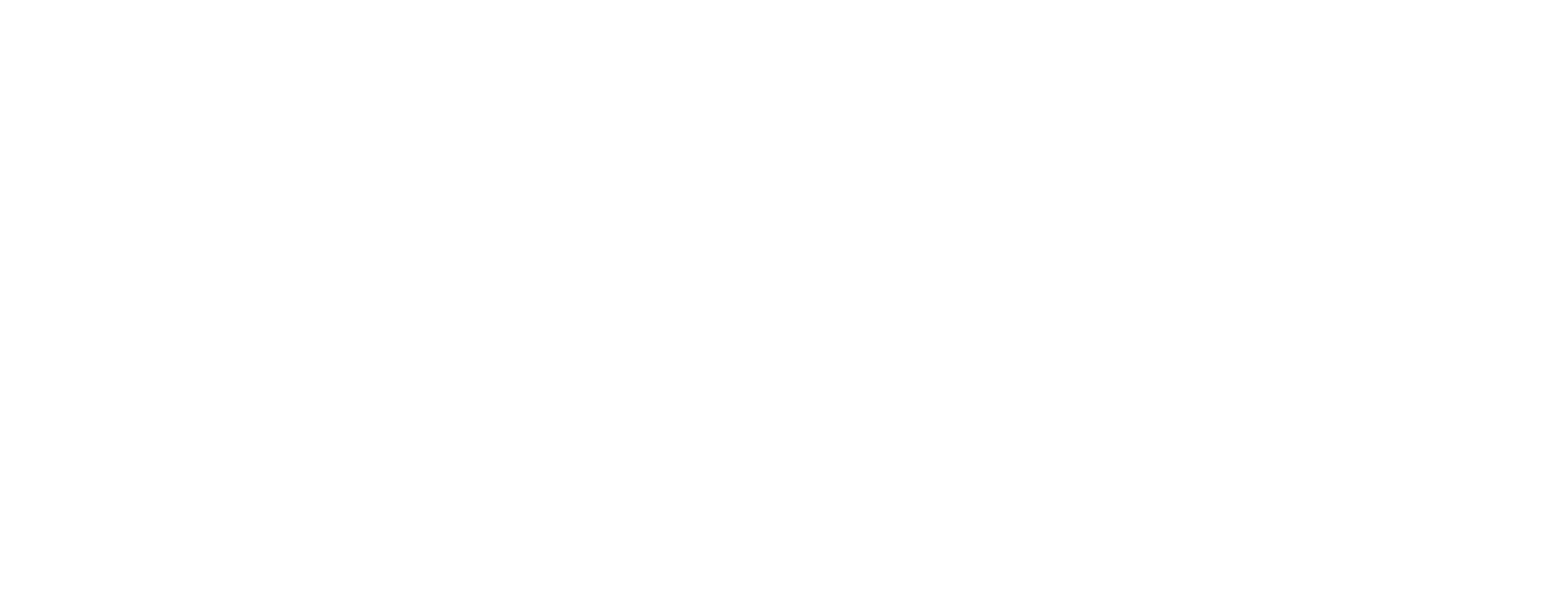
제8조 (표구비 규정)
① 입선 이상 작품에 대해 표구비를 부과하며, 표구는 협회가 정한 표준 옵션 및 가격으로 진행한다.
② 협회에서 제공하는 표구 서비스는 기계배접 방식이 아닌 손배접 방식을 원칙적으로 고수한다.
③ 표구비는 실제 표구 원가를 기반으로 책정하며, 회원에게는 할인 혜택을 제공한다.
④ 작품 규격별 표구비는 다음과 같다.
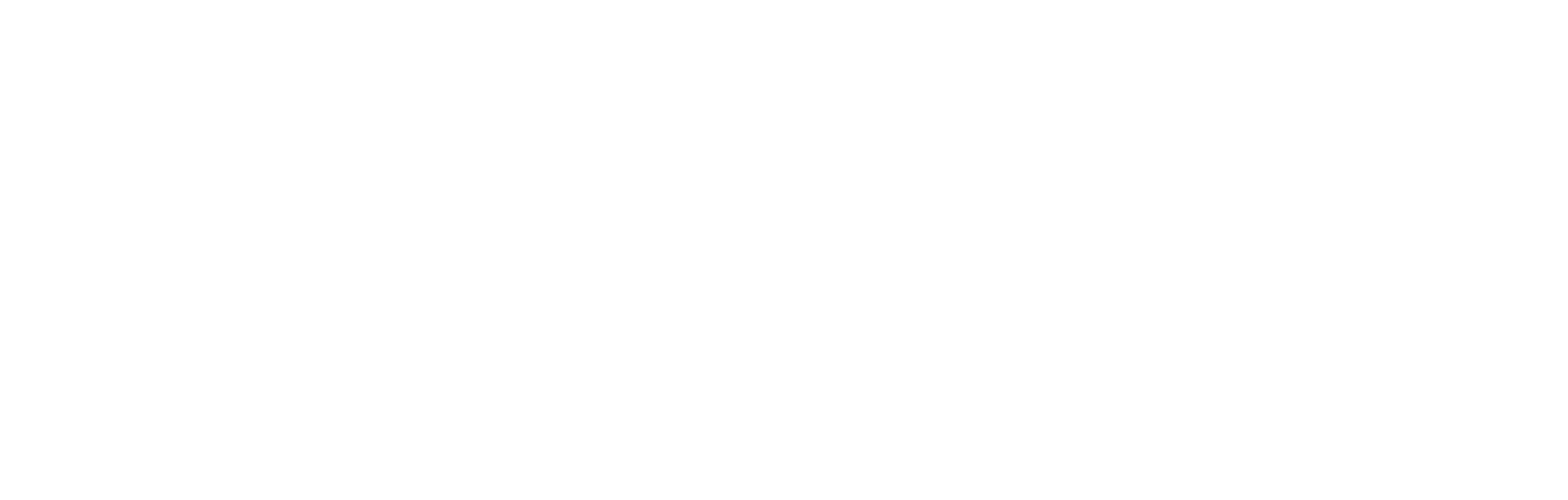
제9조 (도록비 규정)
- 전시 참여한 정회원에게는 도록 1권 무료 제공한다.
- 추가 구매 혹은 전시 참여 정회원이 아닌 경우
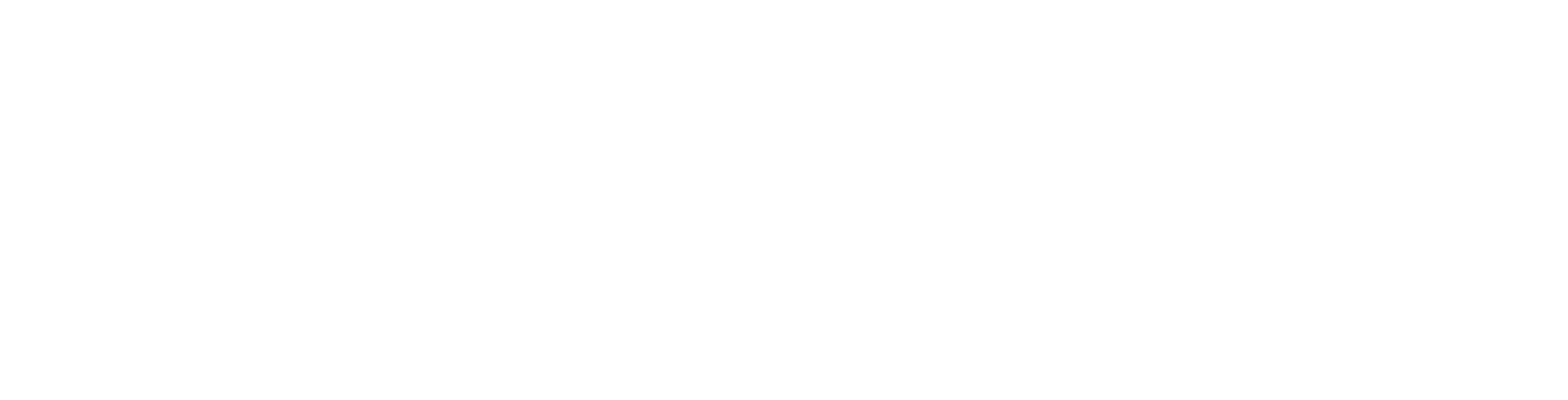
제10조 (작가 개인 홈페이지 초기 구축비 및 연간 유지보수비 규정)
① 홈페이지 제작 및 유지보수 계약을 체결하고 연간 유지보수비를 납부한 정회원은 해당 연도의 연회비가 면제된다.
② 전시에 40점 이상 작품을 출품한 작가에게는 다음의 혜택을 제공한다.
가. (최초 혜택) 개인 홈페이지 제작비 및 1차 연도 유지보수비를 전액 면제한다.
나. (지속 혜택) 2차 연도부터는 연간 유지보수비만 납부하면 홈페이지 유지보수 서비스를 지속적으로 제공받으며, 해당 연도의 연회비는 면제된다.
③ 전시에 30점 이상 출품하신 작가에게는 초기 구축비 면제되며, 해당 연도의 연회비는 면제된다.
④ 전시에 20점 이상 출품하신 작가에게는 초기 구축비의 50%를 할인한다.
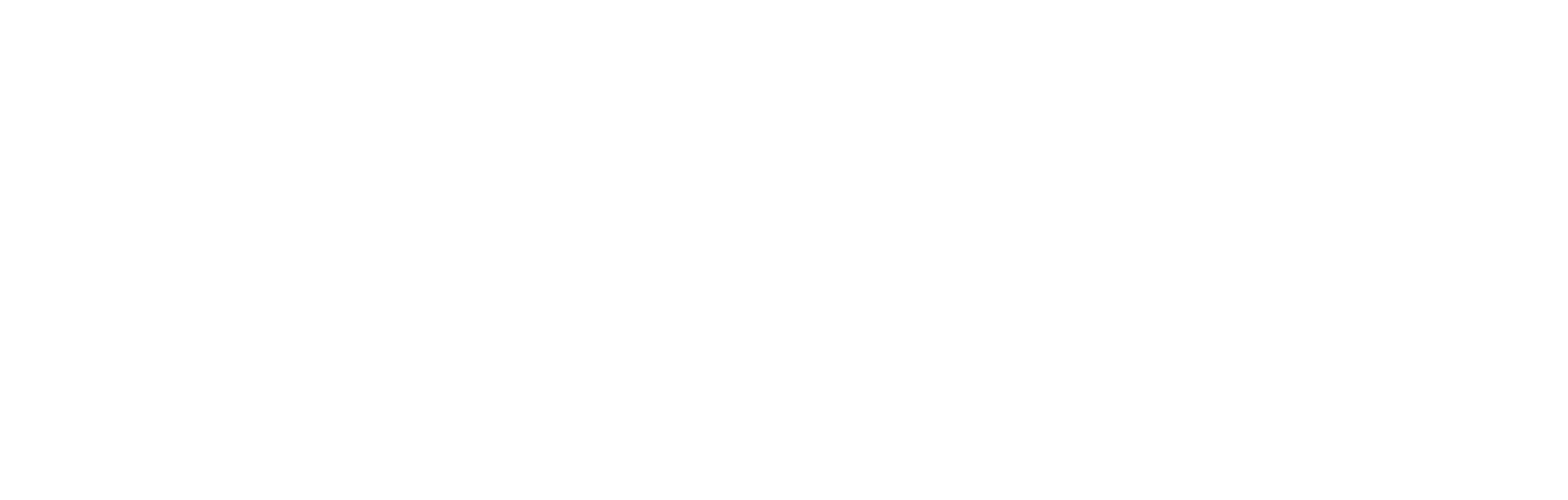
제10조의 2 (단체 홈페이지 구축비 및 연간 유지보수비 규정)
① 본 조는 2인 이상의 작가(양인전, 연합전, 단체전)가 공동으로 홈페이지를 구축 및 운영할 경우의 비용을 규정한다.
② (회원가 적용 기준) 참여 작가 전원이 본회의 정회원일 경우 회원가를 적용한다. 참여 작가 중 비회원(또는 자격 정지 회원)이 1명이라도 포함될 경우 표준가를 적용한다.
③ (회원가) 회원가 기준 초기 구축비 및 연간 유지보수비는 다음 표와 같다.
.png)
④ (표준가) 표준가(비회원 포함) 기준 초기 구축비 및 연간 유지보수비는 다음 표와 같다.
.png)
⑤ (추가 옵션 및 할인) 다국어 지원, 온라인 도록 시스템, 작품 판매 기능 등 추가 옵션 비용과 조기 계약, 장기 계약 등에 따른 할인 정책은 이사회의 의결을 거쳐 별도의 운영 지침으로 정한다.
⑥ (혜택 중복 적용 불가) 제10조(작가 개인 홈페이지) ②항, ③항, ④항에 명시된 전시 출품 수량에 따른 구축비 면제 및 할인 혜택은 개인전 홈페이지에 한해 적용되며, 본 조의 단체 홈페이지에는 중복 적용되지 아니한다.
제11조 (납부 방법)
① 모든 비용은 온라인 납부(계좌이체, CMS 출금 등)를 원칙으로 한다.
② 온라인 결제 시스템을 통해 납부하며, 구매자가 원할 경우 전자 영수증 발급 가능하여야 한다.
제12조 (정회원 기본 혜택)
① 정회원 공통 혜택
가. 전시회 참가할 경우 도록 1권 무료 제공
나. 출품비, 표구비, 도록비 할인가 적용
다. 작가 개인 홈페이지 구축하실 경우 연회비 면제
② 추천작가 이상 추가 혜택
가. 초대작가 후보 등록 기회
나. 특별 전시회 및 해외 교류전 참가 우선권
다. 요건 충족시 작가 개인 홈페이지 초기 구축비 선별 지원
③ 초대작가 이상 추가 혜택
가. 상임이사 후보 등록 기회
나. 특별 전시회 및 해외 교류전 참가 우선권
다. 요건 충족시 작가 개인 홈페이지 초기 구축비 선별 지원
④ 임원 혜택
가. 운영위원 및 심사위원 위촉 기회
나. 특별 전시회 및 해외 교류전 참가 우선권
다. 작가 개인 홈페이지 초기 구축비와 연간 유지보수비 1년 면제
라. 초대작가전 출품비 5% 할인
제13조 (고령 회원 혜택)
만 70세 이상, 가입 기간 10년 이상인 회원 중 협회 발전에 기여한 공로가 다음 각 호의 기준에 따라 현저하다고 인정되는 경우, 이사회 심의를 거쳐 연회비 면제 혜택을 부여할 수 있다.
① 협회 주요 전시회 5회 이상 참여
② 협회 주최 세미나 및 워크숍 강연 3회 이상
③ 협회 사업 기획 및 실행에 핵심적인 역할 수행 등
이때 공로 심의는 별도로 마련된 '공로 심사 기준'에 따라 객관적으로 이루어지며, 필요시 '공로 심사 소위원회'를 구성하여 평가할 수 있다.
부칙 (附則) <2026. 1. 1.>
제1조 (시행일)
본 규정은 이사회의 의결을 거쳐 공포한 날부터 시행한다.
제2조 (준용규정)
본 규정에 명시되지 않은 사항은 이사회의 의결에 따른다.
제3조 (개정)
본 규정을 개정하고자 할 때에는 이사회의 의결을 거쳐 정기총회에 상정하고, 총회의 최종 의결로 개정할 수 있다.
운영 및 심사 규정
Operating & Examination Rules
[시행 2025. 2. 8.] [제3호 시행령, 2026. 1. 1., 일부개정]
제1조 (목 적)
이 규정은 정관 제41조에 따라 사단법인 동양서예협회(이하 “본회”라 칭한다.)의 운영위원 및 심사위원 위촉과 심사방법 등 전시 운영 전반에 관한 사항을 규정함을 목적으로 한다.
제2조 (구성과 임무)
① 운영위원은 운영위원장과 운영위원으로 구성하고 대한민국 동양서예대전의 원활한 운영을 위해 기여하여야 한다.
② 심사위원은 심사위원장과 심사위원으로 구성하고 대한민국 동양서예대전의 공정한 심사를 통해 입상작품을 선정한다.
제3조 (자 격)
본회의 운영위원 및 심사위원의 자격은 다음 각 항과 같다.
① 본회 초대작가 (자문위원, 고문 포함)
② 다른 서예 단체 초대작가
③ 본회 고문이나 자문위원이 추천한 인사
제4조 (위촉방법)
이사장은 대한민국 동양서예대전 개최 1개월 전에 심사 건수를 기준으로 인원을 정하되 2배수를 추천하여 이사회 의결을 통하여 위촉을 결정하고 위촉증서를 수여한다.
제5조 (심사부문 및 규격)
대한민국 동양서예대전의 공모작품 규격은 국전지(70×200cm), 전지(70×136cm), 반지(35×136cm)로 하고 공모 부문은 다음과 같이 6개 부문으로 하며, 필요할 경우 이사회 의결을 거쳐 심사부문을 추가할 수 있다.
① 한글 (한글정자ㆍ정자혼용ㆍ한글반흘림ㆍ반흘림혼용ㆍ한글진흘림ㆍ판본체, 민체 등)
② 한문 (갑골ㆍ금문ㆍ 전서ㆍ예서ㆍ해서ㆍ행서ㆍ초서)
③ 현대서예ㆍ 캘리그라피
④ 전각ㆍ서각 (목각ㆍ석각 포함)
⑤ 문인화, 동양화, 채색화, 수묵화, 민화
제6조 (심 사)
① 옛 법첩을 기준하여 작품을 선정하되 서체별 구성, 여백, 조화, 묵색에 중점을 두고 작품성의 우열을 결정한다.
② 점획ㆍ결구ㆍ장법ㆍ조화의 완성미를 심사하되 다음 표의 여러 요소 들을 비교 심사한다.

③ 심사계획 및 준비
가. 심사위원장은 심사 개시 전 [별표 1] 심사계획서를 작성하여 다음 사항을 명시한다:
- 심사일정 및 진행방식
- 부문별 심사위원 구성
- 평가기준의 세부 적용방안
- 작품 진열및 검토 방식
나. 접수된 작품에 대해 심사번호를부여하고, 작가정보를 봉인하여 익명성을 보장한다.
다. 심사위원장은 심사 전 평가기준에 대한 사전교육을 실시한다.
④ 심사진행 및 평가방식
가. 각 심사위원은 [별표 2] 심사표를 사용하여 각 항목별 배점은 다음과 같다:
- 점획(點劃): 25점 (평가요소: 방원, 곡직, 경중, 장로, 형질 등)
- 결구(結構): 25점 (평가요소: 대소, 소밀, 허실, 향배, 호응 등)
- 장법(章法): 25점 (평가요소: 농담, 강유, 완급, 여백, 구성 등)
- 조화(調和): 25점 (평가요소: 기운, 아속, 미추, 통변, 창신 등)
나. 평가는 5점 단위로 채점하며, 각 항목별 평가근거를 간략히 기재한다.
다. 심사위원별 총점을 산출하고, 최고점과 최저점을 제외한 평균점수를 최종점수로 한다.
⑤ 심사의견 작성
가. 심사완료후 각 심사위원은 [별표 3] 심사의견서를 작성한다:
- 한글 부문 심사평
- 한문 부문 심사평
- 현대서예ㆍ캘리그라피 부문 심사평
- 전각ㆍ서각 부문 심사평
- 문인화, 채색화, 수묵화, 민화 부문 심사평
- 전체 심사평 및 개선제안
나. [별표 3] 심사의견서에는 출품작의 전반적 수준, 특징적 경향, 우수작품의 특성 등을 포함한다.
⑥ 종합평가 및 결과집계
가. 심사위원장은 [별표 4] 심사결과종합표를 취합하여 다음사항을 정리한다:
- 작품별 심사위원 평가점수
- 최종 평균점수 산출
- 순위 및등급 결정
나. 등급결정 기준:
- 90점 이상: 대상 및 최우수상 후보
- 85점 이상: 우수상 후보
- 80점 이상: 특선 후보
- 75점 이상: 입선 후보
다. 동점자 발생시 처리방안:
- 조화(調和) 점수가 높은 작품우선
- 장법(章法) 점수가 높은 작품우선
- 심사위원 간 협의를 통한 결정
라. 대상 선정: 90점 이상을 획득한 작품이 2점 이상일 경우, 심사위원 전원의 투표를 거쳐 최종 대상을 결정한다.
⑦ 심사결과 확정
가. 심사위원장은 종합심사 결과를 이사장에게 보고한다.
나. 이사회는 심사결과를 검토하고 최종 승인한다.
다. 확정된 심사결과는 수상자에게 개별 통보하며, 협회 홈페이지에 게시한다.
제7조 (시상 내역 및 상금)
① 제6조의 심사 결과에 따라 선정된 입상작에 대하여 다음과 같이 시상한다.
② 제6조의 심사 결과에 따른 입상 등급은 본상(本賞), 특별상(特別賞), 특선(特選) 및 입선(入選)으로 구분한다.
③ 각 입상 등급별 세부 내역, 선정 인원 및 상금은 다음과 같다.
가. 본상 (작품의 예술성을 최우선 기준으로 선정)
- 대상: 1명, 상장 및 상금 200만원
- 최우수상: 1명, 상장 및 상금 100만원
- 우수상: 2명, 상장 및 상금 30만원
나. 특별상 (서예의 균형 있는 연구와 다체(多體) 출품 장려)
- 오체상: 3명, 상장 및 상금 20만원
- 삼체상: 4명, 상장 및 상금 15만원
다. 기타 입상
- 특선: 30명(조정 가능), 상장
- 입선: 50명(조정 가능), 상장
④ 제3항의 특별상은 여러 서체에 대한 작가의 다각적인 노력과 연구를 장려하는 협회의 운영 방침을 반영하여 책정한다.
⑤ 제3항에 명시된 시상 인원(특선, 입선 포함)은 당해 연도 출품작의 총수 및 작품의 전반적인 수준을 고려하여 이사회의 의결로 조정할 수 있다.
⑥ 제3항 외에 협회의 재정 상황이나 특별 후원 유치 시, 이사회의 의결을 거쳐 추가적인 특별상(예: 후원사상, 이사장상 등)을 신설하여 시상할 수 있다.
⑦ 상금에 부과되는 제세공과금은 수상자 본인 부담을 원칙으로 한다.
⑧ 시상식 및 상금 지급에 관한 세부 절차는 이사장이 별도로 정하여 공지한다.
제8조 (임 기)
운영위원 및 심사위원의 임기는 위촉일로부터 당해년도 대한민국 동양서예대전 종료일까지로 한다.
부칙 (附則)
부칙 <제1호, 2023. 08. 24>
제1조 (시행일) 이 규정은 공포한 날로부터 시행한다.
부칙 <제2호, 2025. 02. 08>
제1조 (시행일) 이 규정은 공포한 날로부터 시행한다.
부칙 <제3호, 2026. 01. 01>
제1조 (시행일) 이 규정은 공포한 날로부터 시행한다.
제2조 (경과조치) 이 규정 시행 이전에 기획된 전시에 대해서는 종전의 관례에 따른다.
전시 관리 및 운영 규정
Exhibition Management and Operation Rules
[시행 2026. 1. 1.] [제1호 시행령, 2026. 1. 1., 신규 개정]
제1장 총 칙
제1조 (목 적)
이 규정은 사단법인 동양서예협회(이하 "본회"라 한다)가 주관하거나 대행하는 전시회의 기획, 홍보, 작품 판매 및 운영 전반에 관한 사항을 규정하여, 전시 사업의 효율성을 높이고 회원의 권익 보호 및 창작 활동 지원을 목적으로 한다.
제2조 (적용 범위)
본 규정은 본회가 주최, 주관, 후원하거나 회원(또는 외부 작가)의 위탁을 받아 수행하는 모든 전시 관련 수익 사업 및 대행 업무에 적용한다. 다만, 대한민국 동양서예대전의 심사 및 운영에 관한 사항은 별도의 규정에 따른다.
제2장 전시 대행 및 기획 지원
제3조 (대행 업무의 범위)
본회는 신청 작가의 개인전 개최를 지원하기 위하여 다음 각 호의 업무를 대행할 수 있다.
- 전시장 대관 예약 및 행정 절차 대행
- 전시 기획, 연출 및 진행 보조
- 온·오프라인 홍보 마케팅
- 기타 전시 개최에 필요한 제반 사항
제4조 (비용 부담 및 후원)
① 전시 대행에 소요되는 대관료 및 제반 비용(도록 제작, 운송, 설치, 철수 등)은 수익자 부담 원칙에 따라 참여 작가가 전액 부담한다.
② 단, 이사장은 작가의 역량, 본회 기여도, 재정 상황 등을 고려하여 직권으로 소정의 후원금을 지원하거나 대행 수수료를 감면할 수 있다.
③ 작가는 확정된 소요 비용을 대관료 납부 기한 10일 전까지 본회가 지정한 계좌에 예치하여야 한다.
제4조의 2 (신진작가 발굴 및 예술활동 지원)
① 본회는 청년 및 신진 작가의 발굴과 예술인 등록(예술활동증명) 지원을 위하여 협회가 주최하는 기획 전시(인큐베이팅 전시 등)를 운영할 수 있다.
② 본 기획 전시는 참여 작가의 비용 부담을 줄이기 위하여 공동 전시(부스전 또는 그룹전) 형태로 진행하되, 예술활동 실적 인정이 가능하도록 작가별 독립된 전시 공간과 도록 지면을 배정하여야 한다.
③ 참가비는 대관료, 도록 제작비, 홍보비 등 실 소요 비용을 감안하여 이사회의 의결로 정한다.
④ 본회는 참가 작가가 한국예술인복지재단의 예술활동증명을 원활히 등록할 수 있도록 표준계약서 체결, 실적 확인서 발급 등 행정 편의를 제공한다.
제3장 전시 홍보 대행
제5조 (홍보 대행 서비스)
① 본회는 전시 작가의 효과적인 작품 홍보를 위하여 다음 각 호의 서비스를 유료로 제공한다.
- 본회 공식 홈페이지 및 SNS 채널 게시
- 회원 대상 문자 메시지 발송 및 뉴스레터 게재
- 주요 포털 사이트 및 미술 커뮤니티 정보 등록 대행
② 홍보 대행 수수료는 1개월 기준 금 330,000원(부가가치세 포함)을 원칙으로 하되, 물가 상승 및 서비스 범위에 따라 이사회의 의결로 조정할 수 있다.
제6조 (신청 및 납부)
홍보 대행 서비스를 이용하고자 하는 자는 소정의 신청서를 작성하여 제출하고, 서비스 개시 7일 전까지 수수료 전액을 납부하여야 한다.
제4장 작품 판매 및 정산
제7조 (판매 수수료 및 정산)
① 본회가 주관하거나 대행하는 전시 기간 중 작품이 판매될 경우, 판매가는 작가가 책정한 가격을 기준으로 한다.
② 본회는 판매 대행에 따른 카드 결제 수수료 및 제반 행정 비용으로 최종 판매가의 30%를 수수료로 징수한다.
③ 수수료를 공제한 나머지 70%의 금액은 판매 대금 결제가 완료되고 전시가 종료된 날로부터 14일 이내에 작가에게 지급한다.
④ 판매와 관련하여 발생하는 제세공과금(소득세 등)은 관련 법령에 따라 처리한다.
제5장 보칙
제8조 (실적 증명서 발급)
① 본회는 본회가 주관하거나 대행한 전시에 참여한 작가가 정부 및 지자체의 예술 지원 사업 신청(예술인 패스, 창작준비금 등)을 위해 실적 증빙을 요청할 경우, [예술활동 실적 증명서]를 발급하여야 한다.
② 제1항의 증명서 발급 수수료는 회원의 경우 무료로 하며, 비회원의 경우 소정의 발급 수수료를 징수할 수 있다.
제9조 (계약의 해지 및 환불)
① 작가가 개인 사정으로 전시 대행 또는 홍보 대행 계약을 취소하고자 할 경우, 다음 각 호의 기준에 따라 환불한다.
- 서비스 개시(홍보물 게시, 대관료 납부 등) 7일 전까지: 전액 환불
- 서비스 개시 7일 전 ~ 1일 전까지: 총비용의 50% 환불
- 서비스 개시 이후: 환불 불가
② 이미 지출된 비용(대관 계약금, 디자인 비용 등)은 환불 금액에서 제외하고 실비 정산한다.
제10조 (손해배상)
전시 진행 중 작가의 귀책사유로 인하여 본회 또는 제3자에게 손해를 끼친 경우, 작가는 그 손해를 배상하여야 한다.
제11조 (기타)
본 규정에 명시되지 않은 사항은 이사회의 의결 또는 일반적인 관례에 따른다.
부칙 (附則)
부칙 <제1호, 2026. 01. 01>
제1조 (시행일) 이 규정은 공포한 날로부터 시행한다.
제2조 (경과조치) 이 규정 시행 이전에 체결된 전시 대행 계약은 종전의 관례에 따른다.
제1장 총칙
제1조(목적)
이 규정은 정관 제41조에 따라 사단법인 동양서예협회(이하 "본회"라 한다)의 추천작가 및 초대작가 선정에 관한 사항을 규정함을 목적으로 한다.
제2장 자격 심사 및 선정
제2조(선정방법)
① 추천작가는 다음 각 호에서 정하는 점수를 합산하여 10점 이상 취득한 자 중에서 선정한다.
② 초대작가는 다음 각 호에서 정하는 점수를 합산하여 15점 이상 취득한 자 중에서 선정한다.
③ 2024년부터는 전통부문과 현대부문으로 분리하여 추천작가 및 초대작가 증서를 수여한다.
제3조(수상실적 배점기준)
① 대한민국 동양서예대전 입상자 배점
1. 입선: 1점
2. 특선: 3점
3. 삼체상: 5점
4. 오체상: 7점
5. 우수상: 7점
6. 최우수상: 8점
7. 대상: 9점
② 본회 주최 국제서예전람회 수상실적은 제1항의 배점과 동일하게 적용한다.
③ 입상작품이 화첩에 수록된 경우 0.5점을 추가 가산한다.
④ 대상 수상작품이 국립박물관 또는 미술관에 소장된 경우 1점을 추가 가산한다.
⑤ 같은 해 입상점수는 최고점수 하나만 인정한다.
제4조(지회 전람회 배점기준)
① 본회 지회 주최 전람회의 수상실적은 다음 각 호와 같이 차등 배점한다.
1. 광역시‧도 규모: 2점
2. 시‧군‧구 규모: 1점
② 3년 연속 수상실적 보유 시 1점을 추가 가산한다.
③ 같은 해 대한민국 동양서예대전 또는 타 지회 전시회 취득점수가 있을 경우에는 최고점수 하나만 인정한다.
제5조(학력 및 경력 가산점)
① 서예 관련 학력에 대해 다음 각 호와 같이 가산점을 부여한다.
1. 서예관련학과 학사학위 취득 및 수료자: 2점
2. 서예관련학과 석사학위 취득 및 수료자: 추가 1점
3. 서예관련학과 박사학위 취득 및 수료자: 추가 2점
② 다음 각 호의 경력에 대해 가산점을 부여한다.
1. 서예관련 자격증 보유자: 1점
2. 전통서예 전수자(공인된 서예가 문하생): 2점
3. 해외 서예관련 학위 취득자: 동등 학위 수준으로 인정
제3장 심사절차
제6조(자격심사위원회)
① 자격심사위원회는 다음 각 호의 위원으로 구성한다.
1. 초대작가 5인 이상
2. 외부 전문가 1인 이상
3. 이사회에서 선임한 위원
② 위원의 임기는 2년으로 하며, 연임할 수 있다.
③ 심사의 공정성을 위해 위원 중 과반수는 신규 위촉하여야 한다.
제7조(심사방법)
① 심사는 연 2회 실시하며, 서류심사와 작품심사로 구분한다.
② 작품심사는 최근 3년 이내 제작된 대표작품 3점을 대상으로 한다.
③ 심사위원 전원의 3분의 2 이상 찬성으로 자격을 부여한다.
④ 신청자는 별지 서식 "추천・초대작가신청서"를 작성하여 제출하여야 하며, 자격심사위원회의 심의를 거쳐 이사장이 최종 선임한다
제4장 자격관리
제8조(자격유지 의무)
① 추천작가 및 초대작가는 다음 각 호의 의무를 이행하여야 한다.
1. 2년마다 자격갱신을 위한 작품 제출
2. 연 1회 이상 협회 주최 전시회 참가
3. 신진작가 지도 및 멘토링 참여
4. 소정의 연회비 납부
② 추천작가 및 초대작가의 자격요건은 다음 각 호와 같다.
1. 추천작가는 본 협회 정회원으로서 3년 이상 활동하고, 본 협회가 인정하는 전국규모 공모전 입상 실적이 있어야 한다.
2. 초대작가는 본 협회 추천작가로서 5년 이상 활동한 경력이 있어야 한다.
3. 전 각 호의 자격요건을 갖춘 자로서 이사회의 심의를 거쳐 이사장이 최종 선임한다.
제9조(자격정지 및 취소)
① 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 자격을 정지한다.
1. 2년 연속 전시회 불참
2. 연회비 2년 이상 미납
② 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 자격을 취소한다.
1. 협회의 명예를 심각하게 훼손한 경우
2. 자격정지 기간이 3년을 초과한 경우
3. 본인이 자격포기를 서면으로 신청한 경우
제5장 특별규정
제10조(특별선임)
① 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자는 이사회의 만장일치 의결로 특별 선임할 수 있다.
1. 서예문화 발전에 특별한 공헌이 있는 자
2. 국내외 서예교육에 20년 이상 종사한 자
3. 문화체육관광부에 등록된 타 서예단체 초대작가
제11조(명예작가)
① 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자는 명예작가로 추대할 수 있다.
1. 30년 이상 초대작가 자격을 유지한 자
2. 만 70세 이상으로서 협회 발전에 현저한 공헌이 있는 자
② 명예작가는 회비 및 출품 의무를 면제한다.
제12조(국제교류)
① 국제 서예교류 활성화를 위해 다음 각 호의 사항을 인정한다.
1. 국제서예전람회 수상실적
2. 해외 서예단체와의 교류전 참가실적
② 해외 서예단체와 상호인증 제도를 운영할 수 있다.
부칙 (附則)
부칙 <제1호, 2023. 08.24>
제1조(시행일) 이 규정은 공포한 날부터 시행한다.
부칙 <제2호, 2025. 02.08>
제1조 (시행일) 이 규정은 공포한 날로부터 시행한다.
제2조(경과조치)
① 이 규정 시행 전에 취득한 자격은 이 규정에 따라 취득한 것으로 본다.
② 제8조의 의무사항은 이 규정 시행일로부터 1년이 경과한 날부터 적용한다.
会員資格と必要条件
メンバーシップの要件と要件
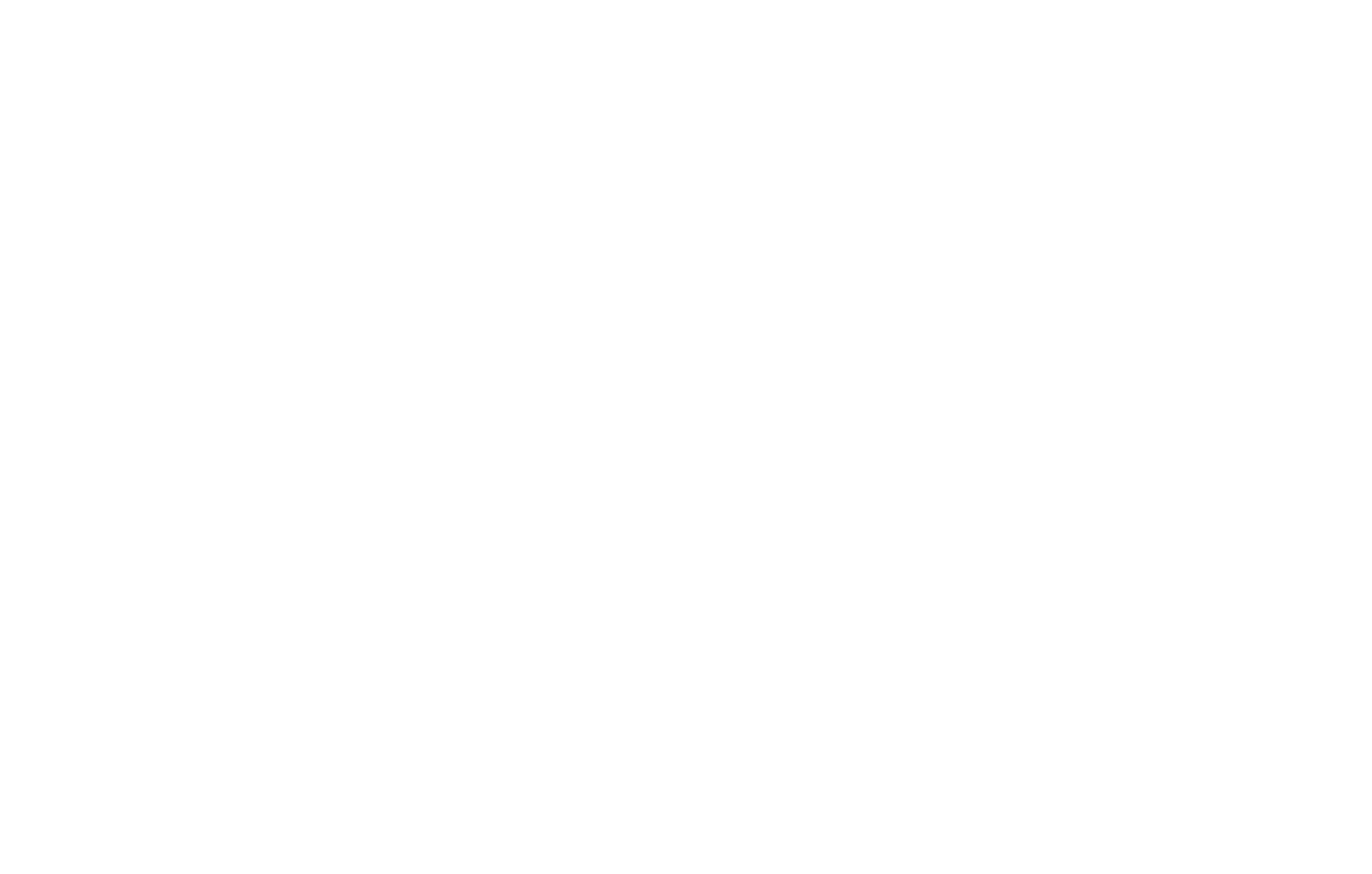
会員資格
- 総会のメンバーは、現在、書道、文学絵画、展示、現代書道、教育、研究に従事しており、その才能を地域社会や個人と共有して研究開発を行うなどのボランティア活動に関心のある人々です。
- 東洋書道協会を設立する趣旨に同意し、所定の登録手続を完了した者。
- 推薦アーティスト、招待アーティスト、役員などの資格」定款について「と」推薦アーティストと招待アーティストを選ぶ際のルール「に準拠しています。
- 추천작가는 3년 이상의 정회원 경력과 수상실적이, 초대작가는 5년 이상의 추천작가 경력이 필요합니다.
メンバーの権利と義務
- 総会のメンバーは、総会が推進する事業について投票権および選挙に立候補する権利を有し、会議に出席し、本会議の活動について意見を述べる権利、および投票に参加する権利を有します。
- メンバーは会議資料や出版物を無料で受け取ることができます。ただし、展示カタログ等は有料で購入する必要があります。
- プレナリーセッションの会員は、所定の入会金及び登録料並びに年会費を支払わなければならず、総会で決議されたすべての事項を遵守する義務を負う。
- 본회의 회원과 임원은 본회가 주최하는 전시회 출품과 각종 행사 참석, 그리고 정관 및 관련 규칙 등 제반규정을 준수할 의무를 가집니다.プレナリーセッションのメンバーは、総会が主催する展示会に参加したり、さまざまなイベントに参加したり、 セット そして 私には規則などを遵守する義務があります。
- 定款第7条第3項に従い、会員が会費及び拠出金を支払わない場合、会員の資格及び権限は停止され、その後会費が支払われた時点でそれらの権利は回復されます。
- 등록비와 연회비 납부는 온라인 모금함을 통하여 진행하며, 마이페이지를 통하여 회원 혹은 임원 본인의 납부내역을 확인합니다. そして カンファレンスWebサイトの右上にあるメニュー」「、」に進んでください「」でメンバー自身の支払い詳細を確認してください。
- 年会費を支払ったすべての正会員と、協会が定める金額を超える開発資金、寄付、寄付金を支払ったアーティストには、引き続き作品を管理および展示できるサイバー空間が提供され、東洋書道協会のウェブサイトに掲載されます。

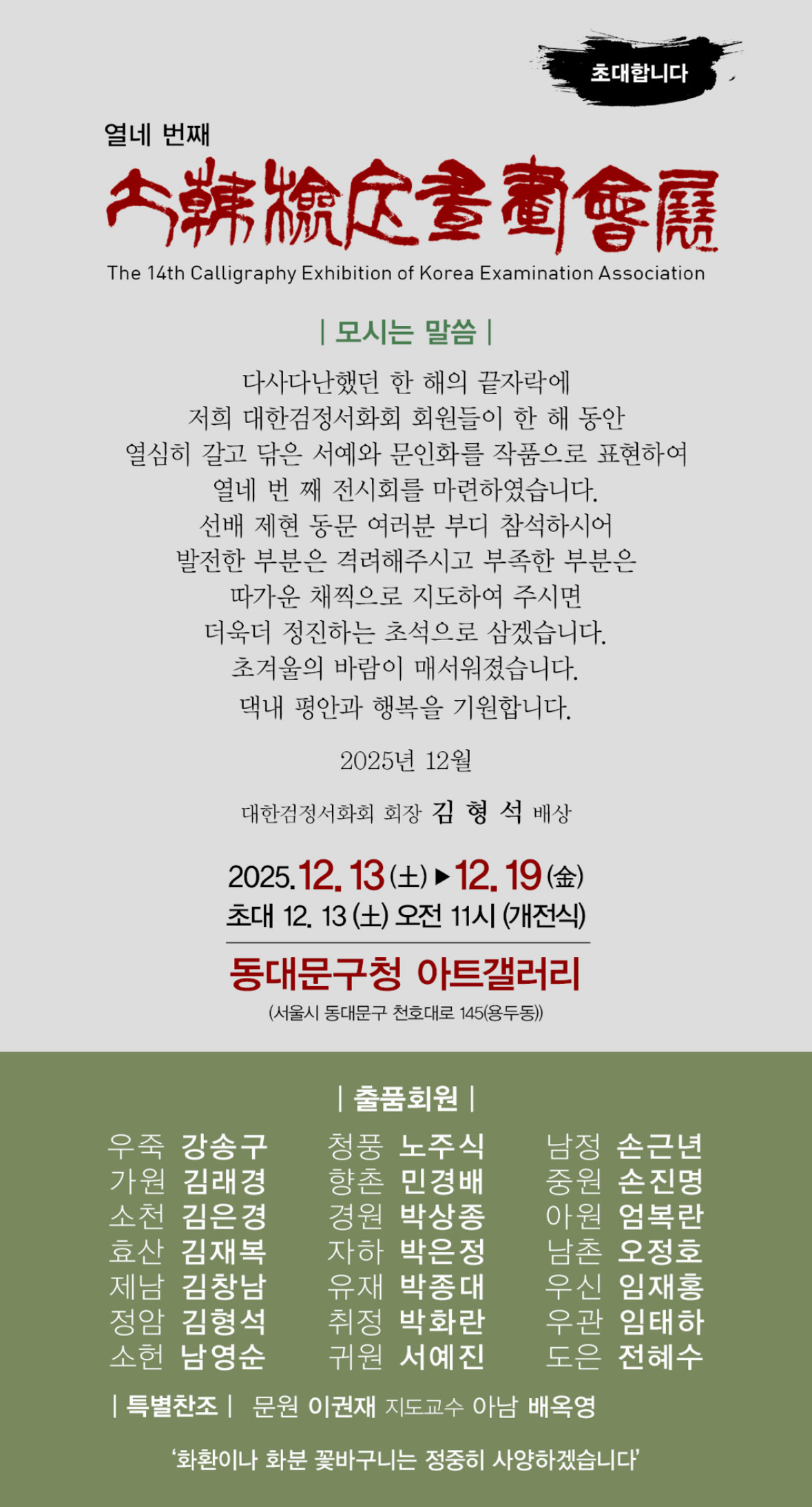
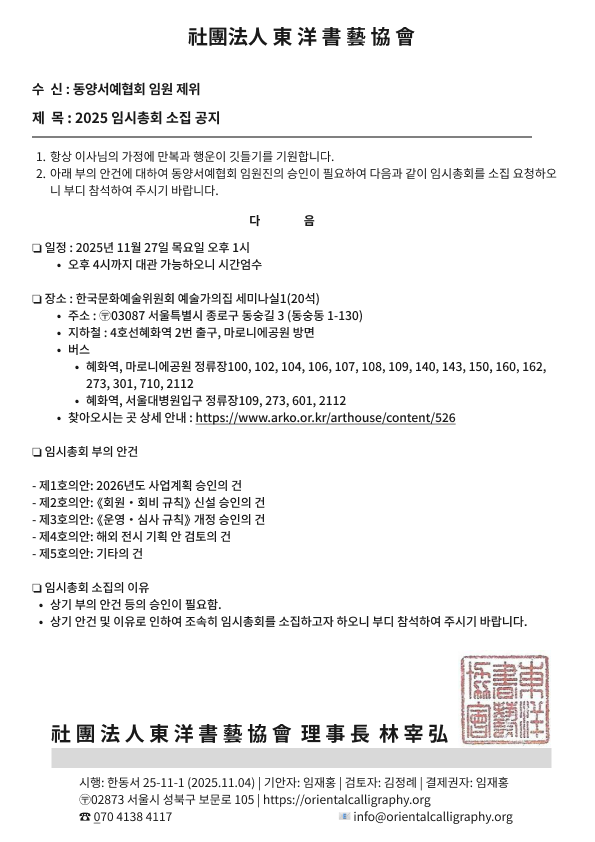

.png)

